| 8. いろいろな経験 (2002/09/18) |
| さて、なんとか高校にも入学できた。「これで専門的に真空管アンプの勉強ができるぞ!」とかなり意気込んで学校に行っていたのだが、世はまさに『IC』の時代、教科書には真空管など「過去の遺産」的な感じで、ほんのチョッとしか書いてなく、なんだか拍子抜けした感じでがっかりしたのだ。この当たり前のことに気が付かなかった自分がとても恥ずかしい。 そして、私の頭脳ではエンジニアになれないことにも気が付いた。「やっぱり野球選手だ!」と思い、野球部に入ろうとしたが、それがなんと『軟式野球』だったのである。『硬式』でなくては意味がないのでそれもあきらめた。 結局、『電子部』のドアを叩くことになり、その中の『オーディオ部』で腕を磨くことにした。良い先輩達に恵まれ、電子工作、ラジオ、テレビなどを作っては色々なことを教わった。テレビを修理、調整する先輩を見ては驚き、私にとって複雑で難しかったプッシュプル・アンプを、作っては調整する先輩達を憧れのまなざしで見ていたのだ。とても良い経験をさせてもらったと思う。 友達も出来、比較的裕福なクラスメートの家に遊びに行くと、『セパレート・ステレオ』と云って、家具調の立派なステレオがたいてい置いてあるのだ。この頃のステレオはまだまだ高価で、持っていることがステータスだったのだ。 この『セパレート・ステレオ』と云うのは、センター・コンソールの両側にそのコンソールと同じようなデザインのスピーカーがある物で、とてもかっこよくその存在感は本当にすごいものがあった。その音を聞かされ、その音の良さに口惜しい思いをし、「いつか俺だって!」とかなわぬ夢を見ていたのだ。そして、そんな高価な物を親に「買って!」などと言える訳がないので、早く社会に出て金を稼ぎたいと思うようになっていた。 そんな感じで『良い音』を色々な所で聞くようになってきた私は、自分のステレオの音にだんだんと不満を持つようになった。特に低音不足が気になってきたのだ。 クリスタル・カートリッジというのは、負荷抵抗を替えると再生する周波数特性が変化するのだ。この特徴?を利用し、負荷抵抗を大きくして(500キロオームを5メガオームに変更)低音の増強を図った。しかし、低音の増大と共にハム音も大きくなってしまい、とても聞くに堪えられなかったので元に戻した。 音の悪さは「プレーヤーのせいだ」と思い始めるようになり、と同時にスピーカーもなんとなく気に入らなくなってきた。そうは云ってもすぐにグレードアップなど出来る訳がなく我慢して使っていたのだ。それでも好きな曲が手軽に聞ける喜びは、そんな不満を忘れさせる『力』があったように思う。 そして、この頃オーディオの世界では4chステレオの嵐が吹き荒れていたのだ。 |
| 7. 自作派へ仲間入り (2002/08/31) |
 先ずはアンプからやっつける事にした。リーマーも買っておいたし、比較的楽にシャーシ加工は終わった。トランスレスだったので穴あけは真空管2本分だけで済んだのだ。 先ずはアンプからやっつける事にした。リーマーも買っておいたし、比較的楽にシャーシ加工は終わった。トランスレスだったので穴あけは真空管2本分だけで済んだのだ。少しでもカッコ良くしようと思ってパネルも取り付けた。 配線も完了し、トラブルも無く音は出たのだがハム音が少し気になっていた。回路図ではフローティング・アースと云って、コンデンサーでシャーシに落としているのだが、あまり効果がなかったように思う。 トランスレスは100Vコンセントの差し込みの向きを間違えると、シャーシと  かツマミに触ると感電するから仕方のない事なのだが・・・今思えばコンセントの差し込み方に注意すれば良い事なので、直接シャーシに落としても良かったのではないかと思う。 かツマミに触ると感電するから仕方のない事なのだが・・・今思えばコンセントの差し込み方に注意すれば良い事なので、直接シャーシに落としても良かったのではないかと思う。スピーカー・ボックスの製作も全く苦にならなかった。小さい頃からノコギリやトンカチが友達だった私にとって、板材のカットはお手のものなのだ。鼻歌まじりで「ギコギコ」と切り出し、「ガン!ガン!ガン!」と釘を打ち、「アッ!」と云う間に組み上げてしまった。 これも早く聞きたいが為のなせる技だろう。隙間だらけだったけど気にしなかった。とても大雑把なのである。 そして、いよいよスピーカーの取り付けだ。 慎重にドライバーを廻す・・・が、皆が一度は経験すると思われる「プスッ!」をいきなりやってしまった。「スーッ」と体から血の気が引いていくのがハッキリと分った。恐る恐るドライバーを引き抜くと、そこには見事な、まあるい穴ぼこがあいていた。 「なんてこったい・・・」私は呆然と見つめていた。目にはいっぱい涙をためて・・・たかもしれない。 気を取り直し穴のあいたコーン紙をなんとか修理し、全てのユニットを取り付けた。もちろんトゥイーターはパラ接続で、ネットワークは適当な値の電解コンデンサーだ。 全てを接続し音を出してみる。当然良い音が出てきた。低音も高音も良く出るとても良い音なのだ。大満足だった。 私にとって、それはもう立派なステレオであった。 |
| 6. 本格的ステレオへの道 (2002/08/22) |
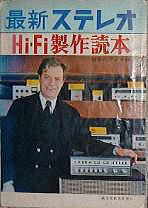 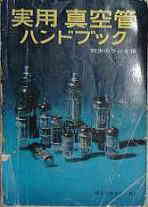 前述の『初歩のラジオハンドブック』と同様に、この2冊は私の師匠とも云える本だ。 前述の『初歩のラジオハンドブック』と同様に、この2冊は私の師匠とも云える本だ。毎日ため息をつきながら隅から隅まで本当によく読んだ。これらの本に書かれている事は今でも頭の中にインプットされている。 特に『実用真空管ハンドブック』はたいへん役に立った。真空管にはそれぞれに役割があり、適材適所で上手に使わなければいけないことを知り、そしていろいろな真空管があることを知ったのだ。 また、『最新ステレオHiFi製作読本』にはたくさんのアンプの製作記事が載っており、そのどれでもが私の心を捉えて離さなかったのである。 中学卒業を間近に控えていた頃だったと思う。そろそろ音に不満を持つようになってきた。私は財布の中身と相談しながら、本格的なスピーカー・システムと真空管アンプを作る計画を立てていた。 アンプは山水のHS-5と云う出力トランスを使った7189シングルを作りたかったのだが、結局いちばんお金の掛からないトランスレスの50BM8シングルに決定した。出力トランスは予算の関係でHiFi用は買えずラジオ用の普及型を使うことにした。 スピーカーはウーファーにコロンビアの20cmスピーカー(テレビ用だと思う)、トゥイーターは同じくコロンビアの8cmコーン型と、ナショナルの5cmホーン型で、確か型番はEAS-5HH31Sだったと思う(あの有名な5HH17とほとんど同じ)。 なぜトゥイーターをダブルにしたのだろうか?しかも違うタイプのトゥイーターでだ。これは今でも謎なのだ。おそらくホーン型の粒立ちの良い高音と、コーン型のやわらかい音をミックスして、すばらしい高音を期待していたのだろう。 さあ、全てが揃い、準備が整った。 |
| 5. 私のステレオ (2002/08/15) |
| その『模型とラジオ』で初めて知ったのだが、アンプを作る場合、通常はアルミのシャーシを使用するのだ。しかし、私にはそれを買う余裕はなかった。手元にブリキ製の手頃なカステラの空き缶があったのでそれを使う事にした。 トランス用の角穴はブリキバサミで切り取り、丸穴はそのハサミの片方の刃を挿しこみ、グリグリと回してこじ開けた。パーツ類は当然手持ちを使用したのだが、おかげでボリュームなんかはシャフトが長すぎて、シャーシからかなり突き出してしまうのだ。その先にツマミが付くのだから、なんともカッコ悪いアンプになってしまった。 配線も完了しスピーカーを繋ぎ電源を入れた。期待と不安が入り混じった気持ちでしばらく待っていた。すると「ブーン」と今まで以上に大きいハム音が聞こえてきたのだ。 「おおっ!?・・・成功したのか!失敗したのか・・・」この時は判らなかった。 神様に祈りながらレコードをかけてみる。スクラッチ・ノイズが聞こえてきた。ついに!遂にやったのだ!この瞬間にようやく、うまくいったことを知ったのである。 音楽が聞こえてきた時の気持ちはとても言葉では言い表せない。以前、ラジオに繋いで音が出た時以上の感動があった。それはそうだ。自分で作ったアンプで音が出たのだから。 外は既に夜が明けていた。もう寝るつもりはなかったので、学校に行く時間になるまでレコードをかけまくった。と云っても数枚しか持っていなかったので同じ曲をくり返し聞いただけなのだが・・・とても幸せなひとときであった。 学校から帰ってくると早速スピーカーボックスの製作にとりかかった。ボックスと云っても15cm位のダンボール箱だ。その箱にスピーカーを取り付けた。これだけでも格段に音が良くなったのだ。 片方にトランジスタ・ラジオ、もう片方にダンボール箱スピーカーに自作アンプと云うシステムが、最初のステレオであった。 私は小さい頃からモーター、豆電球、電磁石等を使った、オリジナルのおもちゃを色々と作って遊んでいた。『電気』と云う見えない『力』の不思議さにとても興味があり、その『力』に秘められた無限の可能性にとても惹かれていたのである。元々電気が大好きなのだ。 高校受験も近くなり、そろそろ進路を決めなければいけない時期になっていた。専門の高校に行き真空管の事を思い切り勉強したかった。私は野球選手になることをあきらめ、迷わず電子の道を選んだ。数学が大嫌いなのにエンジニアになることに決めたのだった |