| 20. CDプレーヤーがやってきた (2021/12/05) |
この「私のオーディオ物語」は、なんと17年ぶりの更新になる。 後輩が勤めている秋葉原のダイナミック・オーディオに、友人と二人で遊びに行ったときのことである。それは忘れもしない1982年10月初旬のことであった。 「○△さん、すごいのが発売されましたよ!聴いてみます?」 「ん?なんだろう??」 最初は何のことなのか分からなかったが話を聞いてみると、それ以前に新聞記事で目にしたことのあるDAD(Digital Audio Disc)のことであった。 「へぇ〜・・・ついに発売されたんだ。聴かせてよ!」 そのときは発売されてから数日しか経ってなく、SONYとDENONの2機種だけだったが、スピーカーとヘッド・フォンでじっくりと聴かせてもらった。 出てきた音は、それはそれは衝撃的で、そのときの印象は今でもはっきりと記憶に残っている。 ・ 音が静か(ボリュームを上げてもうるさくならない) ・ ひずみ感がない ・ 音にすき間がある(表現が難しい) と、いうことだった。特に「音の静かさ」に感激したのであった。 「そりゃー、あんたのシステムがヘボだからそう感じたんだろう」と言われそうだが、決してそのようなことはなかったと思っている。 また、SONYとDENONの音作りの違いはハッキリしていて、前者は派手、後者は落ち着いた音で、ここは好みの分かれるところだろう。 録音の良い音源を聴かされたからとはいえ、その素晴らしさに私の頭はクラクラし通しで、催眠術をかけられたかのようにイスに腰掛け、テーブルに置かれたローンの申し込み用紙にペンを走らせ、気がつけば右手にDENONのCDプレーヤーをぶら下げていた。ふと隣に目をやると、なんとオーディオ・マニアでもない友人も、SONYのプレーヤーをぶら下げている。 うつろな目をした二人は言葉もないまま家路を急いだ。 つづく |
| 19. 直熱3極管 (2005/01/11) |
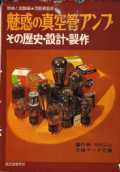  『魅惑の真空管アンプ』、『続・魅惑の真空管アンプ』は私に大きな影響を与えた本である。 『魅惑の真空管アンプ』、『続・魅惑の真空管アンプ』は私に大きな影響を与えた本である。買った当初、ドライバー・トランスを使用したアンプが多く「何を今さら、こんなに性能の悪いアンプばかり・・・」と思っていたのだが・・・ しかし、本を読むにつれ、少しづつ直熱3極管に興味を持ち始めるようになり、その本に掲載されていた2A3シングルを作ってみることにしたのだ。 正直に言うと、ただ古くさい音がするだけだろうと、まったく期待はしていなかった。 それはNFBの掛かったアンプで、出力トランスにラックスのSS5B2.5を使用していたが、入手が難しそうだったのでタンゴのFW-20Sを使うことにし、今までの経験から、負帰還アンプの出力トランスを変えた場合、良いことがなかったので負帰還は外した。 出来あがったアンプの音を聴いてみて驚いた。今でもハッキリと覚えているのは、とにかく元気の良い音がしたことであった。今までとは違う別世界の音だったのである。 「こりゃ、凄いや!」という感じだったのだ。レンジの狭さは感じてはいたが、特に気になるほどのことではなかったような気がする。 それからである。浅野さんが『好きな球』と言っている、「45」、「71A」などを見つけては、買いこむようになり、やがてナス管にも興味を持ち始め、「50」や「300B」など、高価な球にも手を出すようになっていったのである。 ヨーロッパ系の古典管に手を出さなかったのは、姿形があまり好きではなく、良い球だろうと思っていても、とても使う気にはなれなかったのだ。 そして、それらの球でアンプを作っていった。もちろん無帰還である。この頃から、音よりもそれらの真空管の姿の美しさに魅力を感じるようになり、泥沼にはまっていったのだった。 手に持った球にハーッと息を吹きかけ、キュッキュッと磨く・・・きれいになったガラス球を眺めては、ひとりニヤニヤする。もう病気だ。 その後も、アメリカ系の球をずいぶんと買いあさり、一時は入手が可能な古典管をすべて集めようと思っていたくらいである。が、これはあきらめた。 この時には、すでにCDプレーヤーが発売されており、私も使ってはいたが、アンプは時代の流れを逆行していったのである。 |
| 18. 気が付けばコレクター! (2004/05/28) |
|
ユニットは、ウーファーにパイオニア「PW-A31」、スコーカーは磁石の大きさで選んだ、アルテックのフルレンジ「405A」、トゥイーターは色がブラックで格好の良かった、オンキョー「TW-3001」である。このトゥイーターは高かった。 |
| 17. 5極管対3極管 (2004/01/17) |

先ずはアンプだ。近い将来マルチ・チャンネルへの発展を考えていたので、いっきに4台作ることにした。 |